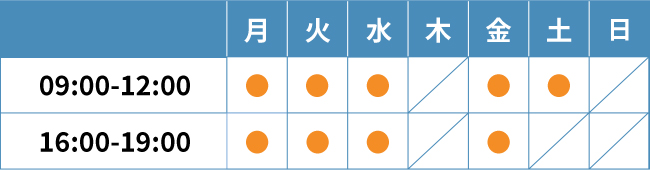花粉症の症状と薬の選び方
鼻の病気|2025.04.01花粉症の薬にはどんなものがありますか?
花粉症の薬は、大きく分けて以下の種類があります。
内服薬(飲み薬)
くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状を抑える効果があります。患者さんそれぞれの症状の種類や強弱に対応するために、様々な薬があります。以前とは違って、眠気や口の渇きなどの副作用がほとんど出ない薬を選択することもできるようになっています。また、スギ花粉症を根本的に体質から治す治療薬として、舌下免疫療法の薬もあります。3~5年間継続する必要はありますが、唯一根治ができる可能性のある治療薬です。詳細は「舌下免疫療法のページ」をご覧ください。
点鼻薬
鼻の中に直接スプレーや噴霧する薬です。鼻のアレルギー炎症を強力に抑える作用があり、くしゃみ・鼻水・鼻づまりのいずれにも効果があります。一般的にステロイド薬が使われますが、全身的な副作用はほとんどなく、眠気や口の渇きなども認めず、安全に使用することができます。一方、ドラッグストアーなどで市販されている点鼻薬には、血管収縮薬が使われていることが多く、2週間以上の長期間にわたって使用すると薬剤性鼻炎を誘発して、余計に鼻の症状がひどくなりますので注意が必要です。
点眼薬
いわゆる目薬と呼ばれる薬で、液体を目に直接滴下します。花粉による目のアレルギーに直接作用して、目のかゆみ・充血・目の腫れを抑える効果があります。
まぶたに塗るクリーム薬
目の外側から。上下のまぶたに塗るクリーム薬で、最近開発されました。薬の成分がまぶたの皮膚から吸収され、目の中まで浸透して目の症状を抑えます。目薬が上手くできない方におすすめの薬で、しかも1日1回塗るだけでOKです。
花粉症の薬はどうやって選ぶの?
花粉症の薬を選ぶ際には、症状の強さや現れ方、体質、健康状態など個人の状態を考慮した上で選ぶことが大切です。
くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの鼻の症状だけなら内服薬や点鼻薬、目のかゆみもあるなら点眼薬やクリーム薬も追加する、といった具合に症状に合わせて選びましょう。また過去に薬で眠気などの副作用が強かった場合には、車の運転や日ごろの仕事内容、学習環境などに応じて薬を選択します。妊娠中や授乳中の場合には服用できない薬もありますので、診察を受ける前に妊娠中や授乳中であることを伝えておくとスムーズです。
ご自身の症状や体質に合わせて薬を選ぶことが効果を発揮するためのポイントです。
また花粉が本格的に飛散する前・症状が出る前から薬を開始する初期療法を行うことが、花粉症の重症化を防いで花粉症に苦しまないための簡単で効果的な治療法ですので、ぜひお勧めします。
花粉症で「まぶたに塗るクリーム薬」って聞いたことが無いのですが...
花粉症の薬というと、飲み薬、点鼻薬、目薬が一般的ですが、最近、まぶたに塗るクリーム薬が開発されました。この薬は花粉やダニなどによる目のかゆみなどのアレルギー性結膜炎の症状を改善する薬です。1日1回、目のまわりに塗ることでお薬の成分がまぶたの皮膚から吸収され、目の中(結膜)まで浸透し作用します。ゆっくりと成分が浸透するため、塗ってからすぐに顔を洗うことは禁止で、塗るタイミングとしては入浴やシャワーなどでメイクを落とした後、寝る前に塗るのがお勧めです。
保険承認されている薬ですので、保険適用の方は自己負担1~3割で処方を受けることができます。医療証をお持ちの方は、医療証の区分に応じた負担額となります。
花粉症で目がかゆいそんな時は...
目がかゆいのは、花粉が結膜(目の表面を覆う膜)に付着し、アレルギーによる炎症を引き起こすためです。このかゆみを抑えるためには様々な方法があります。
目薬(点眼薬)を使用する
花粉症の点眼薬は抗ヒスタミン薬や抗炎症薬が配合されており、かゆみや充血を抑える効果が期待できます。コンタクトレンズを装用したままでも使える目薬もあります。また、市販の洗眼薬で目に入った花粉を洗い流すことも有効です。一方、目薬が苦手な方には、まぶたに塗るクリーム薬もあります。
メガネを着用する
花粉用のメガネはもちろんですが、普通のメガネを着用するだけでも目に入る花粉の量をかなり減らすことが出来ます。
目を冷やす
冷たいタオルや保冷剤などで目を冷やすと、かゆみを抑え炎症を鎮める効果があります。
目をこすらない
目をこすると炎症が悪化し、かゆみが強くなります。我慢するのが難しい場合でも、極力こすらないようにしましょう。
今年は花粉症がひどい・落ち着いている...そのわけは?
花粉症の症状の程度は、その年の花粉の飛散量、個人の体質、健康状態によって大きく異なります。
例えば、花粉の飛散量が多い場合には、症状はやはりひどくなります。アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)が体に多く入ると、アレルゲンから体を守ろうと免疫機能が過剰に反応して、症状もひどくなります。また、睡眠不足や栄養不足などで体力が低下している場合やストレスが溜まっている場合には、アレルギー症状がひどくなることもあります。免疫機能を正常に保つためにも、体力を整えてストレスもコントロールすることが大切です。
自分だけ他の人より遅く花粉症が出る気がします。
アレルギーの原因となっている花粉の種類によって、飛散時期が異なります。例えば春の花粉症の場合、まずスギから飛び始めて、あとから遅れてヒノキが飛び始めます。したがってヒノキの反応が強く出る方の場合は、症状のピーク時期が遅れることがあります。さらに、カモガヤ・オオアワガエリなどのイネ科雑草の花粉症の場合、これらの花粉はヒノキのあとに飛び始めるので、もっと遅れて症状が出てきて、長引く原因となることがあります。また、花粉の飛散量によっても異なり、ごく少量の花粉でも敏感に反応する方や、一定量以上の花粉が飛散しないと症状出ない方もあります。こうした花粉に対する反応の体質の違いによっても、症状の出る時期にずれが生じる可能性があります。
花粉症は薬だけでなく、できるだけ花粉を回避する生活を心がけることも大切です。花粉情報を参考にして花粉の多い日は、洗濯物や布団を外に干さないようにしたり、できるだけ外出を控えたり、帰宅したときは花粉を払ってから室内に入るなど、体の中に入る花粉の量を減らすために花粉対策にもしっかり取り組んでいきましょう。
花粉症の対策について詳しくはこちらのコラムをご覧ください。