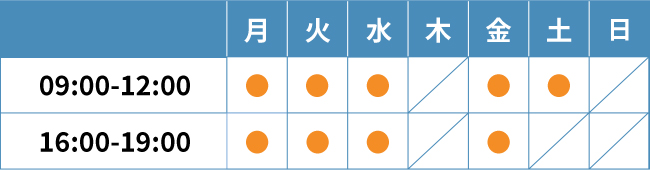耳鳴り
-
耳鳴りとは

周囲で音が鳴っていないにもかかわらず、「ジージー」「キーン」「ボーボー」などの音が聞こえる症状です。耳鳴りには、本人しか聞こえない「自覚的耳鳴り」と筋肉のけいれんや血管病変の拍動などから実際に音が鳴っている「他覚的耳鳴り」がありますが、大半は自覚的耳鳴です。耳鳴りの患者さんの90%程度は、難聴を認めており、難聴と耳鳴りは密接な関係があります。
-
なぜ耳鳴りが起こるのか
自覚的耳鳴が起こる仕組みは、まだ不明な点も多いですが、最近では、難聴に伴って、脳の異常な興奮が起こっている事が関与していると考えられています。
難聴によって、聞こえの情報が脳に伝わらなくなると、脳が音に対しての感度を上げようと働き、異常な興奮状態を起こして、それが耳鳴りとして感じてしまうのです。
また、心理的な要因も関係しており、耳鳴りを不安に思うと、耳鳴りに意識が集中して、さらに耳鳴りの音を大きく感じるようになり、それがストレスとなって不安感も強くなり、ますます耳鳴りを意識してしまうという悪循環に陥ってしまいます。 -
耳鳴りの原因となる病気
最も多い原因は、老化に伴う加齢性難聴ですが、突発性難聴、騒音性難聴、メニエール病、中耳炎、耳垢の詰まりなど様々な耳の病気があります。また、まれですが聴神経腫瘍や脳梗塞もあります。
-
耳鳴りの診断と検査
まずは聴力検査にて難聴の有無を確認します。その上で、耳鳴りの音がどのような音でどれくらいの大きさで聞こえているかを調べるために、ヘッドホンから色々な音を聞いて検査します。めまい症状もある場合には、めまい検査も行います。
-
耳鳴りの治療
急性期の耳鳴りには、まず難聴の原因となっている病気の治療を行います。薬物療法では、内耳の循環改善薬、内耳の神経の働きを良くするビタミン薬、漢方薬、心理的な要因が強い場合には、抗不安薬や抗うつ薬が使われる場合もあります。慢性化した耳鳴りには、薬物療法以外に、心理療法や音響療法もあります。心理療法にて、耳鳴りがなぜ鳴るのか、鳴っている耳鳴りは心配なものではないなどを理解する事で、耳鳴りへの不安を解消するようにしていきます。音響療法は、 補聴器を使って聞こえなくなった音を増幅させて聞く方法などがありますが、毎日継続して長期間にわたって続けていく治療法です。
-
耳鳴りを感じないようにする工夫
耳鳴りは、意識すればするほどストレスになり、それがさらに耳鳴りを悪化させてしまいます。耳鳴りを意識しないような環境づくりや生活を心がけることが大事です。静かすぎる環境を避けて、テレビやラジオや音楽など色々な音を聞きましょう。趣味に熱中したり、適度な運動をするなど耳鳴りを自然に忘れられるような生活も効果的です。
こちらの記事の監修医師 :
医療法人一心会 京本耳鼻咽喉科
院長 京本良一
- 平成5年3月関西医科大学卒業、医学博士号取得。
- 平成5年から平成17年まで大学病院や基幹病院にて勤務。
- 平成17年8月京本耳鼻咽喉科開院を経て現職に至る。
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定専門医
- 補聴器相談医
耳鼻咽喉科専門医として、丁寧で優しい説明・診療を心がけ、小さなお子様からご高齢の患者様まで、「来てよかった!」と安心いただける医療を提供してまいります。