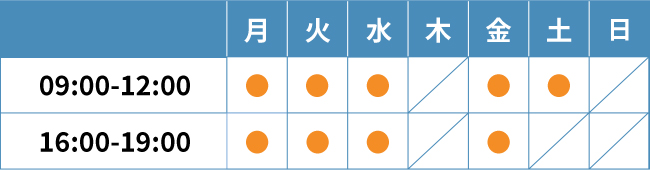口内炎
-
口内炎とは

口内炎とは、口の中の粘膜にできる炎症の総称です。
頬の内側、舌、唇の内側、歯ぐきなどに生じます。
口の中を噛んでしまった、睡眠不足が続いたために口内炎ができたなど、誰しも経験があるかと思います。 -
口内炎の種類
口内炎には、いくつかの種類があります。
●アフタ性口内炎
口内炎の中でも最もよくあるタイプで、典型例では痛みを伴う白色の円形の浅い潰瘍ができ、周囲には赤く炎症を認めます。原因は不明な場合もありますが、睡眠不足・疲労・ストレスなどによる免疫力の低下やビタミン不足・胃腸の不調も関係すると言われています。
通常は1週間から2週間程度で軽快していくことが多いですが、痛みが強い場合は食事や会話がつらくなることもあります。
アフタ性口内炎には、数mm程度の小さなものから比較的大きなものまで、様々なサイズのものがあります。●外傷性口内炎
口の中を噛んだり、歯ブラシで傷つけたり、熱いものを食べてやけどした時などにできた傷口に雑菌が入り込んで、潰瘍や赤みのある腫れができるタイプの口内炎です。
歯列矯正をしている場合に、矯正器具が当たって傷がついてできたり、義歯の刺激でできることもあります。傷口の状態によって痛みの程度は様々ですが、傷口がしみる、熱い感じがすることもあります。●ウイルス性口内炎
ヘルペス・手足口病・ヘルパンギーナなどの原因ウイルスによって引き起こされる口内炎です。小さな水ぶくれができて、その後、潰瘍になり、口の中に多発する場合もあります。
アフタ性口内炎よりも痛みが強く、発熱などの全身症状を伴うこともあります。●カンジダ性口内炎
口の中の常在菌の1種であるカンジダ菌という真菌(カビ)が増殖することによって引き起こされる口内炎です。一般的には口の中に白い斑点や苔状のようなものができますが、舌の発赤や表面の萎縮を生じるケースもあります。
糖尿病や免疫不全の方、喘息の治療で吸入ステロイド薬を使用している方、高齢者などで発症しやすくなります。●アレルギー性口内炎
薬物や歯科治療で用いられる金属などによって引き起こされる口内炎です。
口の中のただれや水ぶくれができて、かゆみを伴うこともあります。●全身疾患に伴う口内炎
ベーチェット病・自己免疫疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病、全身性エリテマトーデス、天疱瘡など)・HIV感染症・白血病などの全身疾患の1症状として起こってくる口内炎です。
口内炎は何度も繰り返し、治りにくい場合が多いです。 -
口内炎の主な症状
口内炎の症状の最大の特徴は、「白色の潰瘍部分の痛み」です。
痛みがひどい場合には、食事や会話に支障をきたすこともあります。その他にも
- 患部の腫れや発赤
- 熱いもの、辛いものがしみる
- 口臭が強くなる
- 発熱やリンパ節の腫れ
などの症状が出ることもあります。
-
口内炎の治療
アフタ性口内炎の場合は1週間から2週間で自然に治癒することが多いですが、患部にステロイド軟膏を塗布することもあります。治癒を早めるためには、歯磨きやうがいで口腔内を清潔に保つことや疲れ・ストレスをためないように気をつけることが大切です。
その他、ヘルペスやカンジダが原因で症状も強い場合は、それぞれ抗ウイルス薬や抗真菌薬を使用することもありますし、外傷性の場合は義歯や歯列矯正器具の調整を行うこともあります。 -
長引く口内炎には注意を!
口内炎は通常1週間から2週間で改善することが多いですが、2週間以上治らない場合には舌がんなどの口腔がんが発症している可能性もあり、注意が必要です。また、頻回に再発を繰り返す場合には、ベーチェット病や自己免疫疾患などの全身疾患の可能性もあります。これらの場合、放置しないで早めの受診をお勧めします。
-
口内炎の予防法
口内炎を予防し悪化を防ぐためには、口腔内を清潔に保ち、免疫力を維持することが大切です。歯磨きを丁寧にすることはもちろん、バランスの良い食事や十分な睡眠をとって、疲労やストレスを溜めないように心がけて、免疫力を下げないようにしましょう。また、口の中を傷つけないために、熱い食べ物でやけどをしないように注意して、義歯が合っていない場合には歯科で調整をしてもらいましょう。