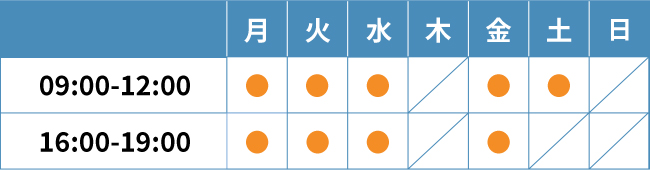咽頭炎
-
咽頭炎とは

咽頭炎とは、のど(咽頭)の粘膜に炎症が起きた状態です。咽頭は図のように上から順に鼻腔の奥の上咽頭、口を開けたときに見える中咽頭、さらに奥の食道につながる下咽頭に分けられます。これらのいずれかに炎症が起きた状態をまとめて咽頭炎と呼びます。
咽頭は外気と直接つながっているため、空気中に潜むウイルスや細菌、ホコリなどが付着しやすく、炎症を起こしやすい場所ともいえます。多くの場合は、ウイルスや細菌などが原因で起こる急性咽頭炎ですが、急性咽頭炎が長期化したり、治ったり繰り返したりして慢性咽頭炎になることもあります。
-
咽頭炎の症状
咽頭炎の症状は、原因や炎症の程度によって様々ですが、のどに関する次のような症状が見られます。
- のどの痛み
- のどがイガイガする
- のどが詰まった感じがする
- 飲み込みづらさ
- 咳
- 声がれ
その他に全身的な症状として、以下のような症状が起こることもあります。
- 発熱
- 体のだるさ、倦怠感
- 頭痛
-
咽頭炎の原因
咽頭炎の主な原因はウイルス感染です。アデノウイルス・インフルエンザウイルス・コロナウイルスのほか、ライノウイルスなど聞きなじみのないウイルスが原因となることもあります。
特に空気が乾燥している秋~冬にはのどの粘膜が乾燥しやすく、ウイルスに対するのどの抵抗力が低下するため、これらの季節には咽頭炎が起こりやすくなります。
また、ウイルスだけでなく溶連菌(溶血性連鎖球菌)を代表とする細菌が原因となることもあり、急性咽頭炎の多くは病原微生物による感染症が原因であるとも言えます。
それ以外の原因としては、喫煙・アルコール・辛い食べ物などによるのどの刺激や胃液ののどへの(逆流性食道炎)、花粉・ハウスダストなどのアレルギー、慢性副鼻腔炎によって鼻水がのどに落ちること(後鼻漏)などがあります。 -
咽頭炎の治療
咽頭炎の治療は、原因や症状によって異なります。最も多いウイルス感染では、ウイルスの種類によっては抗ウイルス薬による直接的な治療を行うこともありますが、基本的には、のどの炎症を抑える薬の服用やうがい薬、のどの処置治療を行い、のどの痛みがひどい場合や高熱が出て体がつらい場合には解熱鎮痛薬も服用します。
溶連菌などの細菌が原因の場合は抗菌薬(抗生物質)をしっかり服用して直接治療を行い、逆流性食道炎・副鼻腔炎・アレルギーが原因の場合はそれぞれの病気に対しての治療を行うこと、喫煙・アルコール・辛い食べ物の刺激が原因となっている場合は、これらを控えることも重要です。
また、鼻水や鼻づまりがある場合には、口呼吸によってのどが乾燥しやすくなるため、鼻の治療も大切です。
鼻への直接的な処置によって、鼻の中にたまっている鼻水を吸い出して、鼻の吸入治療も行い、鼻の症状を和らげる薬の服用や点鼻薬を使用して、鼻の通りを良くしていくことが、のどの症状の悪化を防ぎ、早く治すために重要です。上咽頭に慢性的な炎症がある場合、当院では上咽頭に直接薬剤を塗布するBスポット療法(EAT)も行っています。のどの違和感や慢性的な咳にも効果が期待できる治療です。詳しくはBスポット療法をご覧ください。
Bスポット療法について -
長引くのどの症状には注意を
のどの症状が2~4週間以上続く場合には、咽頭炎ではなく、のどのがんが発症している可能性もあります。
したがって症状が長引く時には放置しないで、早めに耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。 -
自宅でのセルフケア
咽頭炎になった場合、加湿器などで部屋の湿度を保ち(50~60%)、水分をこまめに摂るなどの対処をして、のどの粘膜が乾燥しないようにしてください。
ただし、水分を取るときには、炭酸水や酸味の強い飲み物やアルコールはのどにとって刺激となるため、避けるようにしてください。
食事は刺激の少ないのどに優しい食べ物を食べるようにして、免疫力を高めて回復を早めるために、十分な睡眠と安静を心がけてください。 -
咽頭炎の予防法
咽頭炎の予防で一番大切なことは、手洗いをこまめに行い、人混みや換気の悪い場所ではマスクを適切に着用して、ウイルスや細菌を体の中に入れないようにすることです。また、のどの粘膜を守って咽頭炎にかかりにくくするために、加湿器などを使用して部屋の湿度を50~60%程度に保ち、喫煙は控えるようにしてください。さらに、体の免疫力が低下しないようにすることも重要で、バランスの取れた食事と十分な睡眠を心がけ、ストレスもためないように気をつけてください。一方、逆流性食道炎・副鼻腔炎・アレルギーなどの他の病気が原因となる場合には、これらの病気の治療をしっかり行っておくことも大切です。